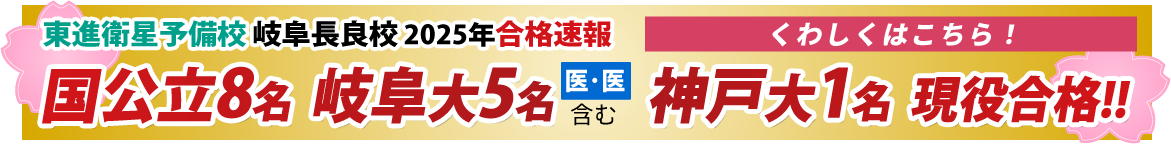大学院入試📖 -建築分野-
こんにちは、担任助手の細谷です。
私は現在、名古屋市立大学芸術工学部建築都市デザイン学科の4年生で、この夏に大学院入試を受けました。合格発表はまだなので詳しい進路は伏せますが、建築分野での大学院入試を経験して強く感じたことがあります。
大学入試との大きな違い
高校生のときの大学入試は「目の前の試験で点を取ること」がゴールでした。数学や英語をどれだけ解けるかが勝負で、ある意味で短期的な成果を目指す試験だったと思います。
一方、大学院入試は「将来の研究や専門分野にどうつながるか」が常に問われました。専門科目の勉強も、ただ覚えるのではなく、「長い歴史の積み重ねの中でどのような立ち位置にあるのか」「建築の設計や都市の課題とどう関わるのか」を考えないと先に進めません。
将来まで見通すことの重要性
特に建築分野では、大学院での研究や設計活動がそのまま将来の仕事や社会への貢献につながります。建築計画、構造、都市デザイン…どの領域に進むとしても、学びの積み重ねが長いスパンで活きることを実感しました。
大学院入試の勉強をしていると、単に「合格するための勉強」ではなく、「この分野でどんな課題に向き合い、どう社会に役立てていきたいか」を考えざるを得ません。ここが大学入試と大きく違う点であり、自分にとっても大きな成長になったと思います。
また、面接では、自分がどのように建築や都市を見ているのか、その価値観や考え方まで問われました。自分の個性は何か、それを考え、引き出すきっかけになったと感じています。
高校生へのメッセージ
高校生のみなさんに伝えたいのは、今の勉強が単なる受験テクニックではなく、将来につながっているということです。私自身、大学院入試を通して「大学に入ったあと、どのように学び続けるか」が本当に大事だと痛感しました。
建築に限らず、どの分野でも学びは積み重なり、将来を形づくっていきます。私もそうでしたが、今は目の前のことに必死だと思いますし、それで十分だと思います。
しかし、大学にな行ったならば、「将来の自分にどう役立つか」を意識しながら、様々な挑戦をして欲しいなと思います。
加えて、もし今大学を迷っている子がいたら、ぜひ、行きたい学部を優先して選んでほしいです。学歴などは大学院への挑戦でいかようにも出来ますが、学ぶ分野は一貫性がないと厳しい面もあります。
特に、建築などの専門性が高い分野は大学院からの学習では間に合いません。
将来の仕事まで踏まえた学部選びをして欲しいなと思います。
何かご質問があれば、いつでも声をかけて下さいね(^^)
お読みいただきありがとうございました!